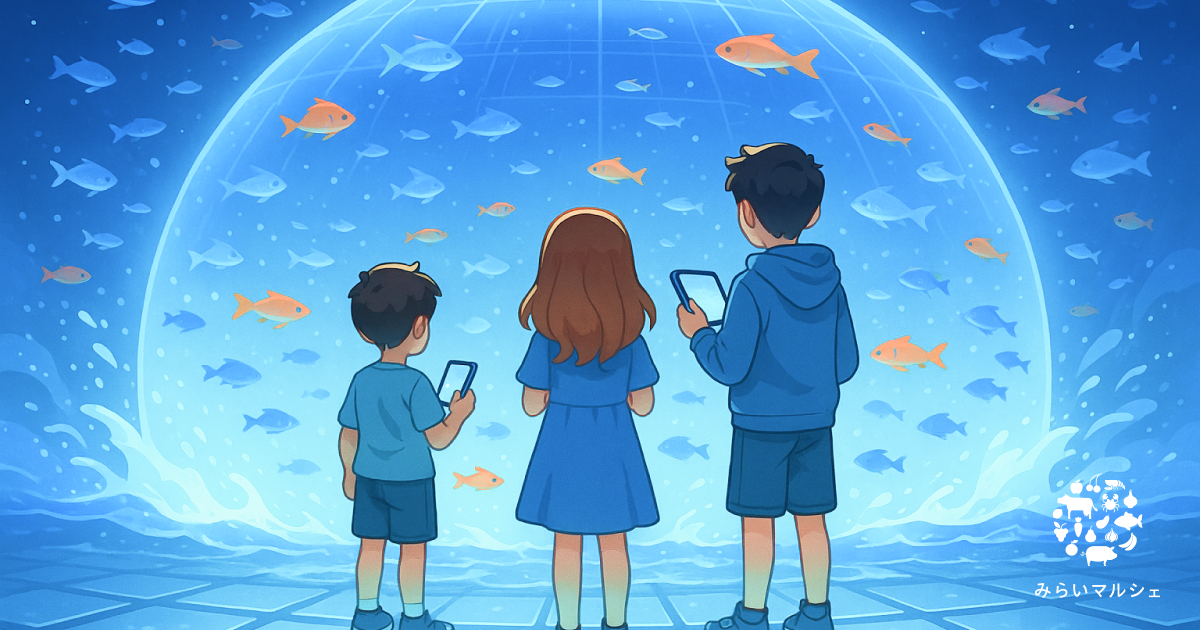
先日、みらいマルシェが大阪・関西万博「BLUE OCEAN DOME (ZERI JAPAN)」に催事出展することをご報告させていただきました。小中学生を対象として、魚が食卓に届くまでのプロセスを遊びながら学ぶワークショップを提供する予定です。
みらいマルシェ、大阪・関西万博「BLUE OCEAN DOME (ZERI JAPAN)」へ出展決定 — 魚のデジタル仕入れ体験で描く、未来の市場
prtimes.jpまずは何より、万博というなかなか経験できることのない舞台に関われること、そして中でも「BLUE OCEAN DOME (ZERI JAPAN)」という、素晴らしい会場とたくさんの価値ある催事の連続の中で、その一端を担えるということに、心から喜びと責任を感じています。
このような素晴らしい機会をつくっていただいたZERI JAPANの皆様、そして、今回のイベントを主催されるフィッシャーマン・ジャパンの皆様に、この場をお借りして深く御礼申し上げます。
実は今回の出展には、大きな迷いがありました。「スモールチーム経営」をしている私たちは、常に「全員が事業に全振り」という状態で、たった1日のイベントであっても、その準備にかける時間と労力は非常に大きな負担としてのしかかります。本当に責任を全うできるか?という不安を払拭するには大きな覚悟が必要でした。
この投稿では、みらいマルシェが今回の出展の意思決定をした背景や、開催に向けた思いを紹介していきたいと思います。
本当に出展すべきか?抱えていた「迷い」
私たちは現在、役員4名、社員0名という少数チームで、ありがたいことに全国33都道府県のスーパー・小売店の方々が日々利用する、生鮮品のプラットフォームを運営しています。
なぜ、あえて小さなチームにこだわっているのか。それは、会社の利益成長を第一目標とするのではなく、得た利益を社会や顧客に還元することで、誰もが当たり前に利用できる 「生鮮品流通の持続可能なインフラ」 でありたい、と考えているからです。
このことは他の投稿でも触れているのでぜひ見ていただけたら嬉しいです。
みらいマルシェが今後もスモールチームにこだわる理由 〜 AI、少子化、Well-beingの時代をどう生きるか
blog.miraimarche.comみらいマルシェが”安い手数料”にこだわる理由
blog.miraimarche.comそんな私たちにとって、今回の出展は、正直に言って大きな迷いとの戦いでした。
一人が何役もこなす今の私たちにとって、イベントの準備にかけられる時間と労力はあまりにも限られています。もしやるなら、本気で取り組みたい。ましてや、未来を担う子どもたちにメッセージを発信するとなると、その責任は計り知れません。
主催者との綿密な打ち合わせ、子どもたちに響くコンテンツの企画と開発、告知やPR、テストと改善、空間演出やノベルティ制作まで——準備は多岐にわたります。
一方で私たちの頭の中には、この業界をより良くするための新しい事業アイデアや、お客様からご要望いただいている新機能の開発リストが常にあります。このイベントに全力を注ぐことは、それらの開発や、新しいお客様との出会いの機会を、先延ばしにすることと同義でした。
「持続可能で豊かな食の未来のために、今やるべきことは、本当にこれなのか?」
私たちは、この問いを何度も自分たちに突きつけました。
なぜ今、表舞台に立つのか —— 水産業の分岐点に向き合うために
創業から6年半、私たちみらいマルシェは、産地とスーパーをつなぐ「流通の裏方」に徹することが、食を持続可能で豊かなものにする最善の道だと考えてきました。
その中で、大きな意思決定をする際には、その意思決定が「魚や野菜をより美味しくするか」「長い目で見て産業の発展に貢献するか」「目の前のお客様を大切にしているか」といったことを自問自答し、今の事業モデルを築いてきました。
しかし、私たちが流通の仕組みをどれだけ改善しようと力を尽くそうとも、水産業全体を取り巻く課題——水揚げ量の減少、担い手不足、消費者の魚離れ——は、もっと大きな次元で、静かに深刻さを増しています。
そして誤解を恐れずに言えば、食の流通は大きな2つの流れの分岐点に立たされていることをひしひしと感じるようになりました。
- 一つは、従来の効率主義をさらに加速させ、「食」を極限まで安く早く、食材が自然の一部であったことすら忘れさせるような流通。資本主義経済の中で採算と利益を重視し、資源をカネに変え、「食」をタスクに変えていく。
- もう一つは、自然との共生の中で、「いただきます」と手を合わせ、そこに人間らしい幸せを再発見するような流通。デジタルとテクノロジーを経済合理性のためではなく、資源保護と食文化の醸成のために使っていく。
もしいま前者がもう一段階進むと、水産資源はより大きなマーケットを求めて多くが輸出に流れ、資源はますます獲り合いになり、日本では一部の富裕層にしか手の届かない希少な高級食品になっていくことは明らかです。そして一度この道を行くと、決して後戻りできないことも強く感じています。
持続可能で、より豊かな「食」を実現するためには、私たちはただ仕組みを変えていくだけではなく、「流通 = 海と食卓の間」を担う私たちだからこそ伝えられるメッセージを発信し、社会と対話しながら文化を育てていく必要があるのではないか——。そして、みらいマルシェを選んでくださったお客様に対して、巡り巡ってその価値をより高めることができるのではないか——。そう考えるようになりました。
今回のイベント出展は、日本の食の未来に対する私たちなりの働きかけであり、お客様への新しい価値提供の形であり、そして、この産業に関わる者としての責任を果たすための、私たちの意志の一つの表れです。
30分のセッションに込める思い
夏休みの貴重な時間を使って足を運んでくださる方々に、どう楽しんでいただき、何を感じていただき、子どもたちの未来に何を残せるのか。
30分という限られた時間で、私たちにできるのは、大人にとっても難しい「流通」の仕組みをレクチャーすることではありません。
この体験を楽しんでいただくことを通じて、子どもたちの心に自然と「なぜ?」という疑問が生まれたり、世界を見る目が少しだけ広がったりする、そんな瞬間をつくることができれば、それが一番のゴールだと考えています。
そして願わくば、スーパーで魚を見たときに、その向こう側にいるたくさんの人々の顔や工夫、さらに海の姿を想像する。食卓に並んだ一皿が、自分が生きる社会や、広大な自然と繋がっていることを感じる。
私たちのワークショップが、そうした想像力のスイッチを押す、小さなきっかけになれたらと願っています。
開催に向けて
イベント当日まで、1ヶ月を切りました。コンテンツの開発もいよいよ大詰め。地域の子どもたちと実際にコンテンツの一部を遊んでみながらブラッシュアップしたり、メンバー同士激論を交わしたりしながら少しずつ仕上げにかかっています。
私たち自身、改めて「未来の市場」の可能性をディスカッションしていく中で、毎日新しい想像が広がっています。
この高揚感を、開催当日に子どもたちと共有し、思い出に残るイベントとできるよう、準備を進めていきたいと思います。