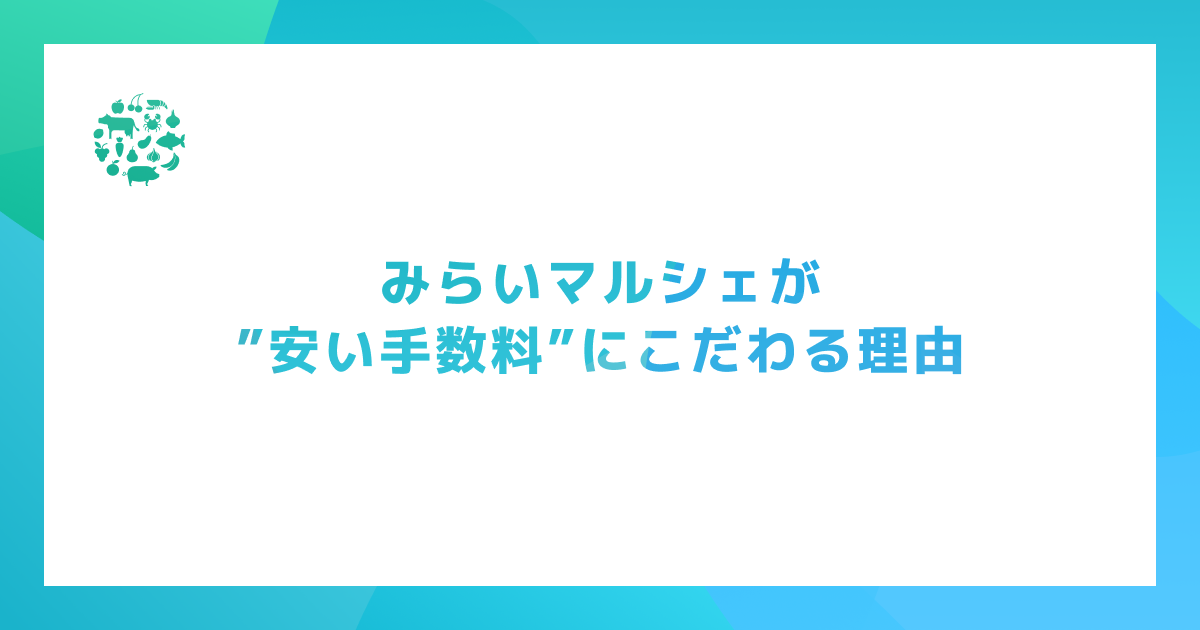
みらいマルシェは創業以来、業界最安値水準である4%の手数料を設定しています。
この「4%」という数字は、単に安いから選んでもらえるといった価格競争の産物ではありません。私たちが目指す「未来の生鮮流通インフラ」を実現するための、明確な意思と設計思想が込められています。
今回は、みらいマルシェがこの手数料に込めた考えについて、少し深掘りしてみたいと思います。
一般的なプラットフォームビジネスと手数料
みらいマルシェは、売り手と買い手を直接つなぐプラットフォームビジネスです。
プラットフォームビジネスのビジネスモデルは、取引ごとに発生する手数料が主要な収益源となるのが一般的です。 多くのプラットフォームは外部からの資金調達(例:VC)を前提に運営されており、その分「収益性の高さ」や「急成長」が求められます。
手厚いサポートと急成長を促進するために手数料は10〜20%と高く設定されることも珍しくなく、成長すれば手数料をさらに引き上げるケースもあります。
しかしこの構造は、強いニーズを持っているユーザーにとっては価値を感じる一方で、幅広いユーザー層に向けては「長く使い続けるには負担が大きい」仕組みになりがちです。
特に生鮮流通のように、利益が小さく、状況が日々変動し、かつ人の手が多くかかる業界では、こうした設計では、現場にしわ寄せがいき、疲弊してしまう構図になってしまいます。
みらいマルシェが目指すのは“持続可能な仕組み”
私たちがつくろうとしているのは、「一時的に使われるサービス」ではありません。目指しているのは、“インフラのように”使い続けられる仕組みです。
水や電気のように、そこにあるのが当たり前で、意識せずとも人々の暮らしを支えている。 しかし、その当たり前は、多くの人たちの絶え間ない努力と支えの上に成り立っています。
もしそこに過剰な負担がのしかかり、支える人や組織が報われず疲弊していくとしたら、その仕組みはやがて静かに崩れていくかもしれません。
本当の意味での「インフラ」とは、誰かの犠牲のもと成り立つものではなく、ユーザーにも無理がなく使い続けられる仕組みが鍵であると思います。
毎日、当たり前のように使われる。 どんなスーパーでも、どんな産地でも、自然と使い続けられる。 そんな流通の“新しい日常”をつくり、食卓が豊かになる仕組みにしたいと考えています。
だからこそ、売り手・買い手のどちらにも“無理がなく続けられる”ことを最優先に設計しています。4%という手数料は、その「続けやすさ」を守るための、私たちにとっての一つの基準なのです。
なぜこの手数料で成立するのか
「4%で本当に成り立つのか?」
実際に、そう尋ねられることは少なくありません。確かに、手数料4%というのは業界の常識からするとかなり挑戦的な数字です。
では、なぜそれが可能なのか?
それは、事業の構造全体を“低コスト前提”で設計しているからです。
私たちは自ら卸売をせず、マッチングに特化する立ち位置を取っています。 物流も自前では抱えず、既存の市場流通網(市場便)や地域の物流資源を活用することで、効率的な運営を実現しています。
さらに、創業から6年間はたった2名で運営してきました。 その間、人員も固定費も膨らませず、“スリムだが筋肉質な組織”として整えてきたのです。
そして、私たちは投資家を入れていません。 それは、利益最大化のためではなく、「ユーザーと社会のための仕組み」を本気で作りたかったからです。
こうした積み重ねによって、4%でも成立する体制を実現してきました。
もちろん、手数料4%にすることで起こる難しさもあります。
例えば
- 一件あたりの収益が小さいので、件数を積まなければ事業が成り立たないこと
- サービス提供に必要な人手・時間・開発費に対して、回収スピードが遅くなること
- リソースの限界があるため、対応の速度に限界があること
それでも私たちはあえてこの水準にしています。
「目先の収益」ではなく「未来の当たり前」を作るためには避けては通れない道だと考えています。
4%はゴールではなく通過点
私たちはこの手数料を、将来的にもっと下げていきたいと本気で考えています。
いきなり1%にするのは難しくても、「社会に根づくインフラ」を目指す以上、手数料は限りなく低くあるべきだと考えているからです。
だからこそ私たちは最初から「スケールしても固定費が膨らまない仕組み」をつくってきました。そうした積み重ねによって、「成長すればするほど安くなる構造」を実現しようとしています。
4%という数字は、その通過点にすぎません。
これは、私たちにとって“今できる最適解”であり、未来に向けた約束でもあるのです。
おわりに
手数料の話は、ただの「料金設定」のように見えるかもしれません。 でも、私たちはそこに、ビジネスのあり方や社会との向き合い方が表れると信じています。
この手数料に込めた思想に共感してくれる方々と、これからの生鮮流通をともにつくっていけたら、こんなに嬉しいことはありません。