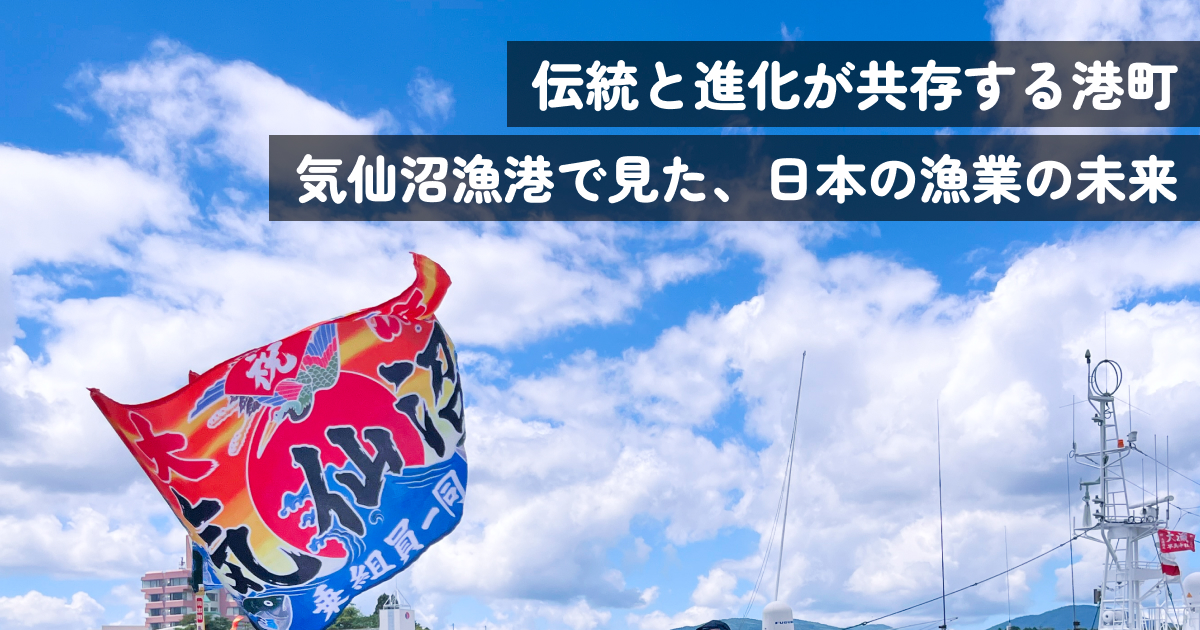
2024年8月、日頃からお世話になっている気仙沼のお客様へのご挨拶のため、気仙沼漁港を訪問しました。
訪問スケジュールを調整している中で、ありがたいことに、大型サンマ漁船のシーズン初出航を見送る気仙沼の伝統行事 「出船(でせん)送り」 にご招待いただき、地元の方々と一緒に参加させていただけることになりました。
出船送りは、街全体が漁船を見送り、安全と大漁を願う大切なイベントで、何十年も続く伝統行事。サンマ漁の船を見送るため、親しみを込めて 「サンマ送り」 と呼ばれているそうです。
当日、気仙沼漁港に向かうと、地元の人々が集まる賑やかな雰囲気に包まれていました。潮の香り、鳴り響く太鼓の音、行き交う人たちの笑い声で、一気にお祭り気分に引き込まれました。どこか懐かしい温かみを感じるのは、家族や友人を見送る気持ちが地域の一体感をつくっているからでしょうか。

晴天の中、たくさんの方が集まって賑やかで温かい空気でした。
出港を祝う紙テープを私もいただき少しだけ参加。これから漁に出る船旅を想像して、私まで気が引き締まるような思いになりました。「この空気をどうすれば食卓まで届けられるんだろう」と想像したりなどしつつ…。

出航を祝う紙テープ。手前に伸びている緑のテープを握らせていただきました。
10隻以上の漁船が一斉に出港し、地域の人々が手を振って送り出していました。その光景は圧巻。地元の方たちの漁業への思いや団結が強く感じられ、胸が熱くなり、私も目一杯手を振らせていただきました。

他の場所から出航した船も港沿いを通ってから沖合に向かいます。勢いのある太鼓で出航を祝っています。

みんなで旗を振ってお見送り。
さて、場面は変わって、翌日は気仙沼魚市場へ。サンマ送りを見た後だと、水揚げされた魚たちの見え方も少し違って感じます。
三陸沖という世界三大漁場の一つに位置するということもあり、気仙沼漁港にはサンマだけではなく地域の名産品が数多く並び、その豊かさに驚かされます。
今回はその代表格であるカツオ、メカジキ、ホヤを見せていただきました。

清潔感のある競り場の一画に整然と並ぶ名産たち。

気仙沼はカツオの水揚げ量が20年以上も日本一。冷凍カツオでは焼津が有名ですが、生カツオでは気仙沼がトップだそうです。

メカジキも気仙沼を象徴する魚で、日本一の水揚げ量を誇ります。

気仙沼といえば名物のホヤ。独特の味わいが特徴。余談ですが私はホヤが大好物。これはテンションが上がります。
気仙沼魚市場では、 最新技術を活用した競りの電子化も進んでいます。
誰がどの価格で入札したのか、結果がその場でわかる仕組みになっており、効率的かつ透明性の高い運営が実現されています。
使っている方たちのお話を伺うと、導入当初は抵抗もあったものの、使っていくにつれてメリットを実感し、慣れも味方して今では手放せない仕組みになっているそうです。

皆さんタブレットを手に、静かに入札を進めていらっしゃいました。
電子入札は、業務負担を軽減するだけでなく、分析結果がより良い流通につながったり、スピーディな出荷によって配送できる範囲が広がったりなど、流通全体としてもメリットのある取り組みとして、個人的にも関心の高い領域です。
ですが費用を考えると小さな市場での導入はすぐには難しい面もあり、電子入札を行なっている魚市場はまだまだ少ないのが実状。今回私も初めて見学させていただき、その仕組みや使われ方は大変勉強になりました。
気仙沼漁港を訪れてみて、漁業文化が、地域の暮らしやコミュニティによって支えられていることを改めて強く感じました。サンマ送りのような伝統行事は、地域全体で支えられる温かさと、日本の食文化の背景にある漁業の努力の象徴のようで、世代を超えて受け継がれていくことを切に願うものでした。
一方で、市場では電子化や効率化が進み、未来志向の取り組みも積極的に行われていることにも驚きつつ、明るい未来に向けた確かな前進を感じました。
こうした「伝統」と「進化」が共存する漁業の現場の思いを、私たちの普段の食卓にまでお届けできたら、もっと水産業が盛り上がると信じています。
気仙沼での学びを胸に、これからも漁業文化の魅力を伝え、テクノロジーの力で支えることができればと思います。
気仙沼の皆様、ありがとうございました!